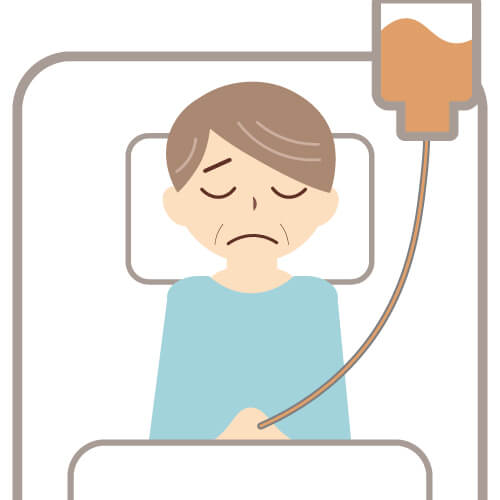延命治療が尊厳を損なう理由
終末期の「延命治療」がいかに人間の尊厳を損なうか。踏み込んで、具体的に述べます。延命治療は、大別して3つの措置が施されます。(1)人工呼吸(2)人工栄養(3)人工透析の3つです。
(1)の人工呼吸の場合、まずは「挿管」を行います。口や鼻から管を入れて呼吸する道を確保するのです。挿管チューブは長く使用できないので、1~2週間で交換するか、それ以上続けなければならない場合は「気管切開」をします。のどに穴を開けて、カニューレ(心臓や血管、気管などに挿入する太めの管)を挿入し、呼吸する道をつくります。「人工呼吸器」を使う場合もあります。この場合は、「非侵襲的陽圧換気療法」(NPPV)と言って、挿管チューブではなくマスクで呼吸器を接続します。
人工呼吸がもたらす状況
いずれにしても、自力で呼吸ができないのですから措置をやめれば死に至ります。
(2)の人工栄養は、口から食事ができなくなったときに取られる処置です。流動食(栄養分と水分)をチューブから入れる方法と血管を使って点滴する方法があります。
チューブ(管)を使う方法で代表的なのが「胃ろう」です。胃に穴を開け、チューブをお腹から外に出します。そのためには内視鏡を使った手術が必要となります。胃ろうに関しては、次回に詳しく述べますが、欧米では回復可能な場合の一次的処置として使われるだけで、日本のように延命のためには使いません。
人工栄養の選択肢と課題
チューブを鼻から入れる方法もあります。「経鼻(けいび)チューブ」と呼ばれ、先端を胃に入れます。1~2週に1回の交換が必要です。抜けやすいので、拘束バンドをする場合があります。
点滴には静脈を使う方法の「中心静脈栄養(点滴)」と、腕などの細い血管から水分とカロリーを補給する方法の「末梢静脈栄養(点滴)」があります。前者は、首や股の静脈を差して、身体の中心部の太い静脈までチューブを入れます。十分な栄養が投与できるので、半永久的に生きることが可能です。チューブは半年に1回程度交換します。ただし、腸を使わないので、消化機能の低下および肝機能障害が起こりやすくなります。
後者は、細い血管を使うので、投与する栄養分は十分とは言えず、徐々に低栄養状態になり痩せていきます。3カ月から1年で亡くなります。
人工透析の苦悩と限界
(3)の人工透析は、糖尿病治療でもわかるように、終末期には腎機能が著しく低下するために処置されます。透析をしないと尿毒症となり苦痛に耐えながら死を迎えます。いったん透析を始めると、やめることはできません。やめることは死を意味するからです。
そのため、透析をやめるには、厳格なガイドラインが設定されています。例えば、高齢で複数の合併症を抱えて、これ以上透析を行うと命が危険になるような場合。患者の状況が極めて不良で、本人の意思がはっきりしている場合などです。言い方は悪いですが、そこまで生かされ続けるのです。
延命治療を避けるための準備
厚労省も推奨しているように「人生会議」=「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」を元気なうちにしておくべきです。家族やかかりつけ医、主治医と話し合って、延命治療の拒否を明確にしておくのです。「生前意思」(リビンググウイル)を具体的に書き残しておくのです。私は、「胃ろう」「中心静脈栄養」「気管切開」「昇圧剤」「輸液」「気管切開」「人工呼吸」「人工透析」などを拒否すると書き留めています。