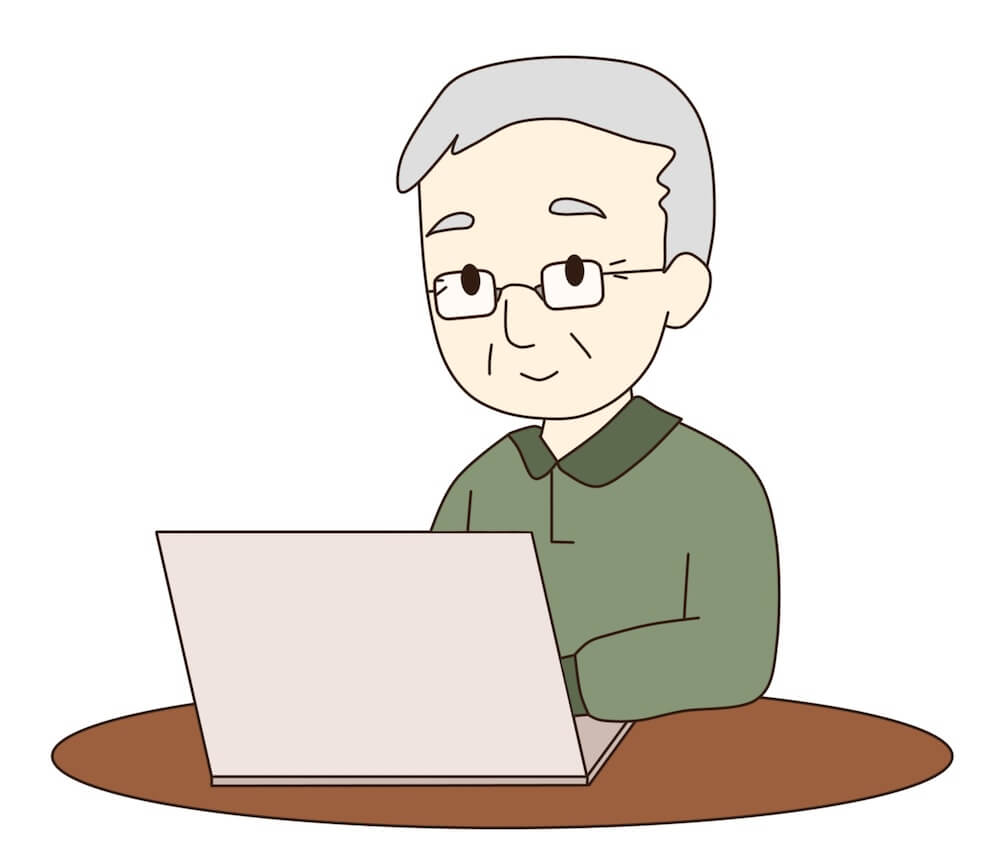「見るだけ」で認知症の段階・種類まで推定
今年5月、日常生活の何気ない視線で、認知症を診断できる新たなAI活用のツールが開発された。その診断法は、わずか10分間、日常シーンの画像を見るだけ。認知症なのか、認知症の前段階の軽度認知障害(MCI)なのか、加えて、認知症の種類、アルツハイマー型認知症とレビー小体認知症なのかについても、高い精度で推定が行えるという。
認知機能低下で視線が変化
「人間は視線によって瞬時にさまざまな情報を得ています。しかし、認知症の患者さんは、認知機能の低下に伴い視線が変化するのです。視線パターンを計測して解析・比較を行い、AIに機械学習させたことで、新たな診断支援ツールの開発ができました」
こう話すのは、筑波大学附属病院認知症疾患医療センター部長の新井哲明教授。認知症の早期段階に対するデイケアなどの治療で成果を挙げ、早期発見・早期診断の方法についても多くの研究を手がけている。
アルツハイマー患者は文字・標識への注意が減少
「アルツハイマー型認知症も、レビー小体型認知症も、健康な人と比べて画面のシーンの少数の場所を見る傾向が強くなり、探索の程度が有意に減少します。その減少傾向が、病気によって異なるのです」
研究では、健常な高齢者、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症のそれぞれの群に、日常生活シーン画像200枚を自由に見てもらい、その視線をアイトラッキング(視線計測)で計測。すると、アルツハイマー型認知症は文字や標識などへの注意が減少した。
たとえば、画面中央に人が映っているとしよう。後ろの壁にカレンダー、手前のテーブルに本が載っていると、健常の場合は、「何月のカレンダーか」「何の本か」を瞬時に観察する。ところが、アルツハイマー型認知症の人は、視線を壁に移動してもカレンダーはスルー。テーブルに視線を向けても本もよく見ないといった状態になる。
レビー小体型は人やモノを見る程度が減少
一方、レビー小体型認知症の人は、画面の中心に視線を向けたまま、人やモノを見る程度が有意に減少するという。
「文字や標識などは高次な画像特徴といい、視線パターンでの注意の減少は、アルツハイマー型認知症の脳の海馬(かいば)や上前頭回(じょうぜんとうかい=前頭葉の一部)の萎縮と相関していました。また、レビー小体型認知症は、画像中心を見る程度が、上頭頂小葉(じょうとうちょうしょうよう)の萎縮と相関していることもわかりました」
上頭頂小葉は、視覚や聴覚の情報を基に自分の立っている位置を把握するなど、重要な役割を担っている。レビー小体認知症では、この部分が萎縮するため、視線のパターンも中心に限られるなど、情報収集に支障が生じるようになるのだ。
海外での活用も可能
「AI診断支援ツールで、軽度認知障害や認知症の原因となる病気の鑑別ができることは、早期発見・早期治療につながります。また、視線のみの診断支援ツールは、言語に関係なく、諸外国での展開も可能です。開発した新たなツールは、臨床と研究のどちらにも有用になると期待しています」。新井教授はこのように手応えを感じている。